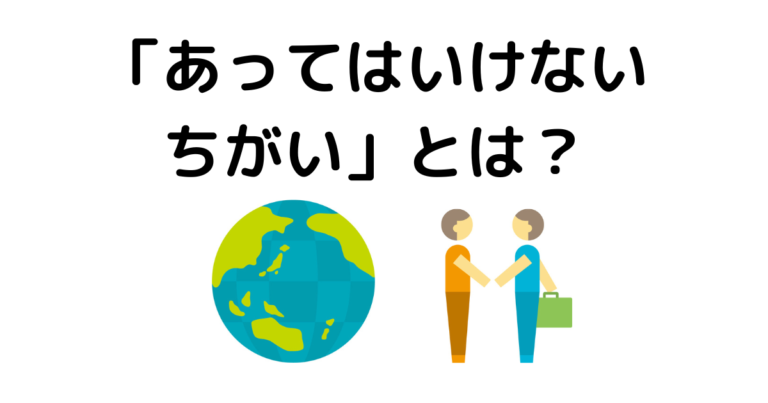地球には多くの人々が住んでおり、みんなで支え合って生きています。そして、人間は一人ひとりに「ちがい」があります。
一人ひとりにちがっているから個性があり、唯一無二の存在になるといえます。
この記事では、身の回りにある「ちがい」について考えていきます。
誤った「ちがい」の認識は危険な側面がある

「ちがっていること」は、一人ひとりが尊い存在としての「個性」として捉えられますが、「ちがっていること」によって差別を合理化させるために利用される危険性をはらんでいることを知っておく必要があります。
差別とは、「十分な証拠なしに、ある人々やグループに対する好悪の感情に基づいて、あるグループに属する人びとを、異なったように扱う行動」(中川, 1998:26人権学習ブックレット④寛容性)であり、「ちがっていること」を理由に不当な扱いを実施することです。
具体的には、文化や価値観、皮膚の色が「ちがう」ことを理由にして、仲間外れをしたり、誹謗中傷を行ったりすることが挙げられます。
「ちがい」に対して、正しく理解したり、考えたりしていくことは、人権教育にとって大切な側面です。そこで、世の中にある「ちがい」が表れる場面について考えていきたいと思います。
「ちがい」について考える
「ちがい」が表れる2つの場面を提示しました。みなさんはこうした「ちがい」はあっていいものだと思うでしょうか。
① Aさんは車の運転免許を取得しているため運転していいが、Bさんは運転免許がないため運転をしてはならない。


② X国の留学生はアパートを借りられるが、Y国の留学生がアパートを借りようとしたら拒否された。


①「Aさんは車の運転免許を取得しているため運転していいが、Bさんは運転免許がないため運転をしてはならない」の場面では、運転に関する資格の「ちがい」による影響が表れています。
資格の取得は本人の意思によって選択することができます。このような本人の意志や努力によって選択することが可能な「ちがい」は「あってもよいちがい」だといえます。
一方、②「X国の留学生はアパートを借りられるが、Y国の留学生がアパートを借りようとしたら拒否された」の場面では、出自に関する「ちがい」による影響が表れています。生まれてくる国を本人の意思によって選択することはできません。
このような本人の意思や努力によっては選択することができない属性の「ちがい」によって社会的待遇に不平等が生じることは、人権に関する問題だといってよいでしょう。
つまり、②のような場面は、「あってはならないちがい」だと、わたしは考えています。また、他にも本人が選択することができなかった属性として、性や民族・人種、親子関係、出生順位等が挙げられます。
こうした出生の瞬間に割り当てられる属性に関する「ちがい」によって社会参加の機会等が平等に与えられない社会は、人権尊重の理念とは程遠いといわざるを得ません。
属性の原理で「ちがい」を判断して安易に行動していくことは、他者の人権を傷付けることにつながってしまう恐れがあるのです。
「あってもよいちがい」と「あってはいけないちがい」
現代社会の多くの国々は、「業績の原理」を優先しており、日本もその一つの国だといえます。
①のような資格の取得や職歴などは、生まれた後の努力や研鑽によって「成し得たこと」として、社会的地位や役割を獲得していくことを「業績の原理」と説明されています(中川, 2000:18)。
なお、日本では、憲法によって法の下の平等が保障されているということは、民主主義社会の基盤として属性よりも業績の原理を重視していると捉えられます。
例えば、プロ野球選手として世界で活躍するAさんの年俸と会社員のBさんの年俸には大きな差異が生じています。
こうした「ちがい」は出自による差異ではなく、Aさんの弛まぬ努力によって手に入れた技術や業績(試合での成績)が社会的な評価を受けた「ちがい」だといえます。民主主義社会において社会的な報酬等に差異が生じることは、業績による「あってもよいちがい」に分類されると私は考えています。

但し、こうした「業績の原理」を貫くための前提として、競争に関する条件を平等にしていくことが社会には求められています。
「あってはならないちがい」によって社会的な不利益を被ったり、日常生活で目にしたりしたときに、「『あってはならないちがい』によって不利益を受けることはおかしい」と感じ取ることは、人権が尊重される社会をつくっていく上で大切なことです。
属性による「ちがい」によって社会的待遇に不平等が生じることは社会全体で解消していくが必要であり、すべての人々に自分らしく生きていくための選択肢を保障していくために条件の平等を整えることが、人権尊重の視点だといえるでしょう。
グローバル化が進展し、言語や文化の「ちがい」について考える機会は多くなってきています。
人間はもともと「ちがい」がある存在であることを意識していくことは、他者に対して寛容な態度をとることにつながることが指摘されています。また、ヨーロッパでは、人権教育のキィ・コンセプトとして「多様な文化や生き方を尊重する―自分とは異なっている点と似ている点を認め合って、ともに生きる―」ことが強調されています(中川,2000: 45)。
こうした点は、国内の人権教育において【自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること】ができるために必要な人権感覚を育成していくことを目指していることと重なりあっています。
参考文献:中川喜代子『人権学習ブックレット④ 寛容性』, 明石書店, 2000.