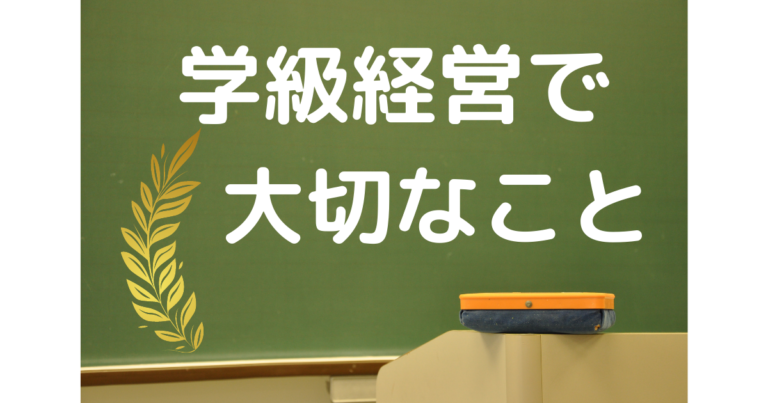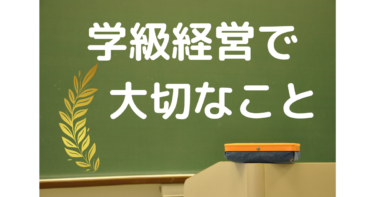小学校の学級担任の仕事において、学級経営はとても重要な役割を担っています。
なぜなら、学級経営は学校教育における「学習活動」と「生徒指導」の基盤となる営みだからです。
学級経営が順調にいっている際には、教師と子どもたちの関係性も良好となり、教師としてのやりがいを感じる場面がたくさん訪れます。
一方で、学級経営が順調にいかない場合は、教師が自分自身を責めてしまう可能性が高まり、自己有用観が感じない場面に遭遇してしまいます。
これまでに、学級経営について悩んでいる先生方を目にすると共に、よりより学級経営を目指して研鑽している先生方とお話をする機会がありました。
学級経営には様々な書籍が刊行されており、様々な方法があります。論者によって、教育への考え方や指導観が問われます。
この記事では、小学校の学級経営で大切なことをお伝えしていきます。
学級経営で悩んでいたり、新しい見方を模索していたりする方の一助になれれば幸いです。
学級経営で大切なこと
教育活動は大きく「学習活動」と「生徒指導」に分類できます。そして、それらの基盤が学級経営です。
つまり、小学校の学級経営は、子どもたちの成長に必要な学び合うための環境を保障することにつながります。
現在は、学校を「チーム」として様々な課題に向けて、組織的に対応していくことが推奨されています。
「チーム学校」を運営していく上でも「学級経営」は学級担任が担う普遍的な要素だといえます。
そして、学級担任は毎年度ごとに変化する営みです(持ち上がりの場合は2年間で変化します)。
つまり、子どもたちの成長に必要な学び合うための環境を保障するために、自らの学級経営を問い続けることが求められます。
すなわち、学級経営では、学級の実態に即しつつ、子どもたちの変化に合わせた運営が大切な観点となります。
何よりも大切な観点は、子どもたちの人権を守るという観点です。分かりやすく表現すると、「みんなの居心地を大切にする」ということです。
なお、学級経営の理論に関しては、「みんなの居心地を大切にするための学級経営の理論について説明します。」をご覧ください。

みんなの居心地を大切にするために人権感覚を育む
先程も確認しましたが、教育活動は大きく「学習活動」と「生徒指導」に分類できます。これらの両方に関わっている営みが学級経営です。
つまり、学級経営は授業中と授業外の両方の場面で機能します。それゆえに、教師の学級経営力は、子どもたちの人権を保障していくための集団作りに大きな影響を与えます。
具体的な方法については、「1%の「もしかしたら」を想像する人権感覚と声かけが、居心地がよい学級経営には欠かせません。」をご覧ください。

何よりも重要なことは、子どもたちの人権感覚を磨き、その輪を学級全体に広げていくことです。
教師は子どもたちを育てるために、指導者としての役割を担っています。子どもたちを管理することに終始するような学級経営では、はじめの方は機能するかもしれませんが、いずれほころびが生じてきます。
そして、管理的な学級経営では、生徒指導の積極的な役割である「自己指導能力」を育むことにつながりません。
学級経営は管理するために実践するのではなく、子どもたちを育てるために実践していくことを忘れてはなりません。
4月から年度末の3月に向かって、子どもたちの成長に向かって学級経営を実践していくという姿勢が大切です。
そのためには、一人一人の人権について考えていくための授業が必要になります。
具体的な人権に関する授業実践については、「自他を認めるための授業実践「震災と人権」の具体例を紹介します」をご覧ください。
学級経営はPDCAサイクルで鍛える

学級経営をサポートするために給食指導や席替えの指導、授業実践に関する記事等を「学級経営で大切なこと<河野辺研究室>」に掲載しています。また、健康を留意していく観点から「週末に心を整えるための方法を紹介します」も掲載しているので、お時間があったらご覧ください。
*2023年8月30日に本を出版することになったことを報告させていただきます。