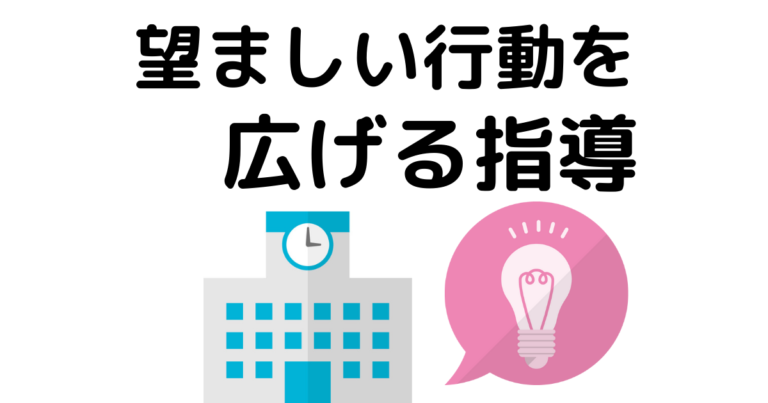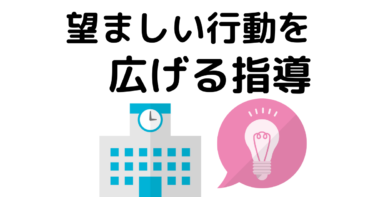学校や教室では様々な行動によって、学校生活が営まれています。人に優しい行動を学級に増やして、人の心をチクチクするような問題行動は、学級の中で減らしていきたいものです。
この記事では、問題行動を減らして望ましい行動を伸ばしていくための方法について紹介します。
「行動のABC」
「応用行動分析学(applied behavior analysis:ABA)」という考え方があります。
これを図解にすると、以下のようになります。
A=「Antecedent:行動の前」、B=「Behavior:行動」、C=「Consequence:行動の後」
A行動の前 →B 行動 →C行動の後
もし、子どもが問題行動をして、それが繰り返されるとしたら、Cの行動の後に好ましい何かを得ていると考えられます。
反対に、望ましい行動を増やしていくためには、望ましい行動の後に好ましい結果を得られると、その行動は繰り返されやすくなります。
そして、その行動を引き起こされるには、Aの環境が行動を引き起こすに影響を与えていると考えられます。
つまり、「行動のABC」では、行動と環境の関係性に着目し、A(行動の前の状況)とC(行動後の結果)を意識して指導していくことで、望ましい行動を促すことに効果的だと言われています。
具体的なB(行動)を見つける
まずは、対象となるB(行動)を具体化することが大切です。
教育活動は、目標があって計画的に指導をしていく営みです。そのため、指導目標に関する具体的な行動を適切にイメージすることが重要です。
つまり、望ましい行動の具体的な姿をイメージすることは、教育活動の目標を具体的に設定するために必要なことなのです。
指導目標を明確にすることができれば、指導計画を具体化させることができます。
例えば、健康観察を行う際に、教師の目と子ども目を合わせることを望ましい行動であることを設定します。その行動を増やすためには、健康観察の際には、座席に座った状態で、教室が静穏である環境を整える必要があります。
そのうえで、教師と目線を合わせてくれている子どもの行動を称賛します。つまり、問題行動を注意するのではなく、望ましい行動を学級全体で認めることを共有し、その行動広げていくことで、問題行動が減少していくことにつながるのです。

小学校1年生を対象とした具体例については、「小学1年生の学級経営のコツを紹介します。」をご覧ください。
C(行動の後)への声かけの工夫
子どもが望ましい行動をしていたとしても、その結果が「報われない」と感じる状況が続くと、その行動は繰り返されることはありません。そのため、教師の意識や声かけは、学級経営において、とても重要です。
ここで注意することは、子どもによって好ましいと感じる言葉や状況は異なるということです。クラスのみんなの前で称賛されることが好ましいと感じる子どももいれば、あまり目立ちたくないと考えている子どももいます。
ここでは、その一例を挙げておきます。
どのような声かけが、その子どもにとって適切なのかは、子どもたちの実態を把握する必要があります。具体的な実態把握の方法は、「学級経営のスタート時期に行うべき子どもたちの実態把握の方法を紹介します。」をご覧ください。
A(行動の前)を整えるための工夫
A(行動の前)の工夫としては、望ましい行動する場面の機会を意図的に設定していくことが考えられます。
例えば、学級経営の三領域の計画的領域(白松:2017)として、学習のきまりごとを明示しておくことで「望ましい行動」を学級全体で共有しておくことが挙げられます。
他にも、自他を認めるための協力的で参加的な学習を取り入れることで、自他を認める体験的な場面を授業として設定していくことも、自他を認めるための学級経営に向けての工夫になります。
授業の詳細は「自他を認めるための授業実践「震災と人権」の具体例を紹介します」をご覧ください。
なお、Cの工夫の同様に、Aの工夫も子どもによって適切なものが異なります。そのため、どのように事前の準備を工夫していくのかを考え続けることが大切です。
問題行動のABC
もし、問題行動が続くという状況であれば、その問題行動のAやCに要因があると考えれます。
例えば、問題行動によってのC(行動の後)としては、他者から注目をされることや、自分の要求が通ること、嫌なことから回避できること等が考えられます。
また、A(問題行動の前)としては、学級経営の三領域である必然的領域や計画的領域が整っていないために、教室に秩序が保たれていなかったり、人他を認める風土が育っていないこと、座席の位置に何らかの問題があるなど考えられます。
このような状況を改善していくためには、問題行動によってのC(行動の後)を把握し、それらの前後の状況に着目をしてその環境を変えていくことも大切です。
問題行動の予防や、問題行動では好ましい結果が得られにくくすると共に、望ましい行動を引き出し、できたときにはその行動に対して好ましい結果へと応えていくことが重要です。
なお、学級集団は複数の子どもたちで構成されています。そのため、学級経営に活かす場合には、多くの子どもたちと教室での望ましい行動(学校や授業中のきまりごと)を学級開きの際に確認することが大切です。
学級開きにおける「B」に関しては、「学級経営方針・学級目標の設定方法について紹介します。」をご覧ください。
スモールステップの目標を設定する
子どもの望ましい行動を増やしていくためには、その行動に対して正の強化を図ることが大切です。
強化とは、「行動の後に本人にとってのプラスの経験が伴い、行動が起きやすくなること」(大久保,2019)です。また、起こりやすくさせるものや行動のことを「強化子(きょうかし)」と言います。
この強化子は人によって異なるために、どのようなフィードバックがその子どもに対して相応しいのかを吟味していく必要があります。
その手順として、目標へのラインを子どもと一緒に確認し、そこに至るまでのスモールステップを設定していく必要があります。
つまり、小さな目標が達成できたことを称賛・承認しながら、成功体験を積み重ねて正の強化を図っていきます。
このような手続きを「シェイピング」と呼んでおり、「ABA(応用行動分析学)」では、一つ一つの階段を上がれるように支援していきます。

最終的には自力でできることを思い描く
教育で大切なことは、学習者が「自分の人生を切り拓いていく資質・能力」を育成していくことです。人生における望ましい行動は、学習者自身が決めていくことです。
そこで、学習者が一人で行動することができることを促していくことが大切です。子どもが課題を乗り越えるために提示するヒントや手かりなどを「プロンプト(prompt)」と呼ばれており、子どもが自力で行動することを促していくことを図っていきます。
プロンプトには、弱いものと強いものがあります。例えば、先生が身体的に誘導させていき、その行動を再現していくものは強いプロンプトになります。一方で、言葉かけだけで学習者に再現を促すことは弱いプロンプトになります。
その中間として、視覚的な手がかりを見せたり、先生がモデルになって見本を見せたりするプロンプトがあります。
失敗を極度に恐れてしまう学習者に対しては、強めのプロンプトから始めて、成功体験を積み重ねながら学習者ができるようにしていくことが考えられます。
一方で、弱めのプロンプトを徐々に強めていくことの方が、「必要最低限の支援」を見つけやすいというメリットがあり、学習者が自力でできることを促すことにつながっていきます。
どちらの方法をとるのかは、学習者の性格や環境、状況などを適切に加味して判断していく必要があります。「行動のABC」とは、あくまでも子どもの一人一人の行動に焦点を合わせて支援をしていくことであり、教師が児童理解を通して、思考し続けていくことなのです。
なお、「行動のABC」は、問題行動を減らして望ましい行動を伸ばしていくための指導方法として活用することができます。しかしながら、学習者のことを常に中心に据えることを忘れてはなりません。
学級経営を整えていくためには、「自分の大切さとと共に他の人の大切さを認める」という人権尊重の理念を望ましい行動であることに加えて、一人一人が尊重し合える社会の実現に向けて指導していくことが大切なのです。
参考文献:白松賢『学級経営の教科書』,東洋出版館, 2017.大久保賢一『3ステップで行動問題を解決するハンドブック 小・中学校で役立つ応用行動分析学』,学研,2019.月刊学校教育相談編集部『月刊 学校教育相談 増刊 シンプルな8つの図が子ども理解・かかわり方を劇的に変える』ほんの森出版,2020.