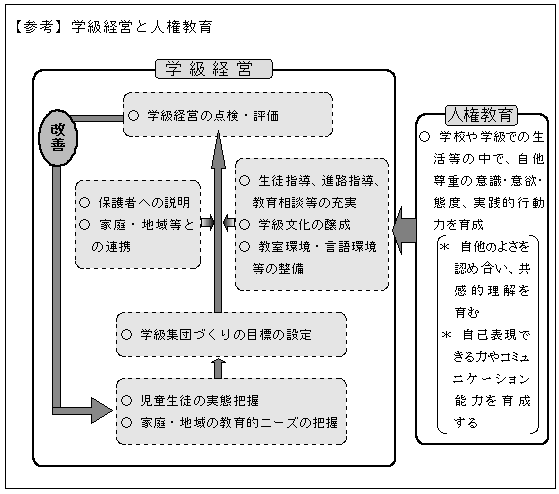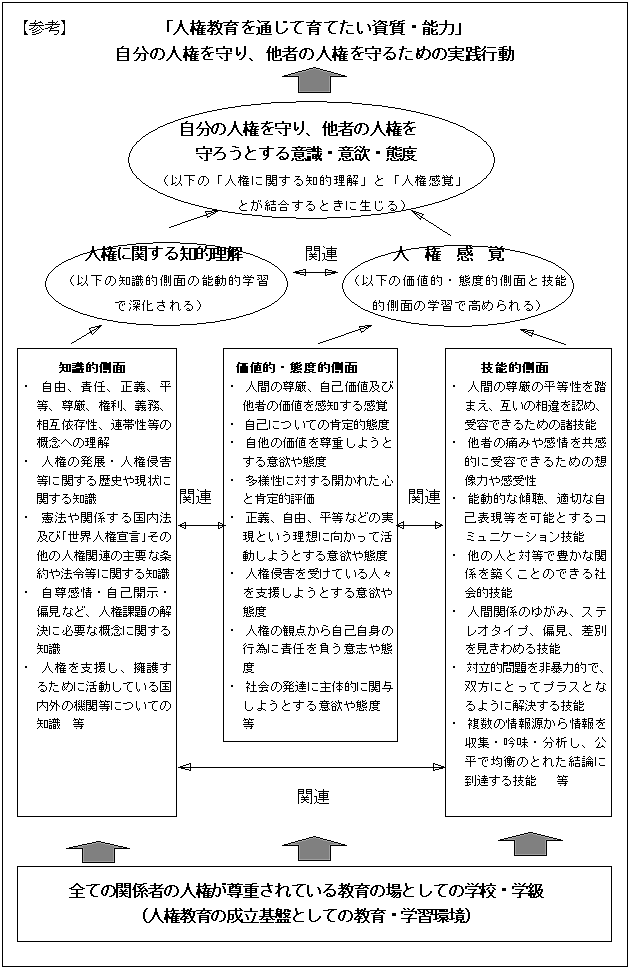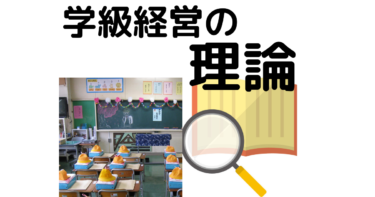学級経営は、日常的な指導の基盤となるテーマです。
授業や生徒指導を実践していく上で欠かすことができない営みであり、1年間という限定的な期間が設定されていることから、学級経営は毎年度リセットされてしまう側面を備えています。
教師は学級経営を毎年度、子どもたちの実態に合わせて実践していく必要があります。教師なら誰でもその重要性を実感しています。
学級経営という言葉はもちろん知っているけれど、それを支える理論が分かりづらいという声を耳にします。
この記事では、みんなの居心地を大切にするための学級経営の理論について説明します。
学級経営の三領域
『学級経営の教科書』(東洋館出版社:2017)の著者である白松賢 先生は、「学級経営の三領域」について説明しています。それは、「必然的領域」と「計画的領域」と「偶発的領域」です。
必然的領域
この領域は、自己と他者の「心と体」を傷つける言動や行動は許さない指導のことを指しており、人権に関する問題を教師が保障をしていく領域です。
この領域が保障されないと、学級の中で暴言などのような他者を傷つける雰囲気が日常化されていき、いじめの問題が起きる可能性が高まります。子どもたちひとり一人の人権を保障する観点のため、全ての教職員が意識して取り組む必要があり、学級経営の根幹に位置づく領域だといえます。
計画的領域
この領域は、教室の秩序化を目指すための条件を整備するための領域です。例えば、給食指導のきまりごとなど、学校での日常生活のルーティーン化するという場面のことを指しています。
この領域は、教室で学ぶ子どもたち全員が学習をしていくためにとても重要な役割を果たします。そのため、子どもたちができるように教師が計画的に指導すると共に、繰り返し指導をすることが求められる領域です。
偶発的領域
この領域は、教師の目が届かない場面であっても子どもたちが自律的に行動することや、急なトラブルへの対応のことに関する領域です。
つまり、教師が管理するというよりも、子どもたちが自分達で考えて行動することや、突発的な事故への対応や保護者の方への対応のように偶発的に起こることを指しています。
教師によっては管理できない範囲のため、児童生徒の好ましい関係や行動になるように働きかける指導が必要となります。
なお、上記の説明は、白松賢『学級経営の教科書』(東洋館出版社:2017)を参考に、わたしが解釈した説明なので、本書を一読することをおすすめします。
みんなの居心地がよくなるために大切な領域
みんなの居心地がよくなるための学級経営をしていくためには、もちろん全ての領域が大切です。
しかしながら、上記の領域の中で優先順位をつけるとしたら、必然的領域がもっとも重要です。
必然的領域は、子どもたちの人権を保障するための指導であり、毅然とした指導を全ての教職員で実践することが必要です。また、教師の人権感覚が問われる領域であると共に、教師が子どもや自分を守るためにも大切な領域です。
この領域を常に意識して指導をすることが教師には求められます。
その次に大切な領域が、教室の秩序化を図るための計画的領域です。
どうして、2番目に大切かというと、この領域の指導は教師によって考え方や方法が異なるために、子どもたちに浸透するために時間を要するためです。すなわち、毅然とした態度よりも、教師が計画的に根気強く指導をしていく領域です。
失敗したとしても繰り返し指導をする心構えが大切であり、子どもたちが間違えたとしてもある程度は寛容に取り組むための領域なのです。
上記の領域は、教師が管理する観点が強い領域です。そのため、教師の学級経営によって教室の秩序を築いていきましょう。そのうえで、偶発的な領域に備えたり、自律的な行動を促していくことが大切です。
人権教育の観点による学級経営の理論
次は、必然的領域に重点を置いた人権教育の観点の学級経営の理論について説明します。
文部科学省(2008)は、人権教育における学級経営について以下のように述べています。
児童生徒が、多くの時間を過ごすそれぞれの学級の中で、自他のよさを認め合える人間関係を相互に形成していけるようにすることが重要であり、このような観点から学級経営に努めなければならない。
なお、学級経営と人権教育の関係性の以下のように表示しており、①児童生徒の実態の把握→②学級集団作りの目標の設定→③地域や保護者との連携→④生徒指導や言語などを含めた学級の風土の醸成→⑤学級経営の点検・評価による改善→① 児童生徒の実態の把握 というようにPDCAサイクルを理論として説明しています。
そして、学級経営の中で、「自他のよさを認め合い、共感的理解を育む」ことや「自己表現できる力やコミュニケーション能力を育成する」ことを通して、自他尊重の意識・意欲・態度、実践的行動力を育成することを意識的に指導していくことを推奨しています。
引用:文部科学省:人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]-指導の在り方編-, 2008
人権教育を通じて育てたい資質・能力
自他尊重の意識・意欲・態度、実践的行動力を育成を目指す上で重要なことは、これらの一連の学級経営を実践しながら、「人権教育を通じて育てたい資質・能力」を図るための授業実践を併せて実践していくことです。
引用:文部科学省:人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]-指導の在り方編-, 2008
「人権教育を通じて育てたい資質・能力」は主に3つの側面(「知識的側面」、「価値的・態度的側面」、「技能的側面」)があります。それらをバランスよく育成していくことが、自他の人権を尊重していく行動へとつながります。
1.知識的側面
この側面の資質・能力は、人権に関する知的理解に深く関わるものである。
人権教育により身に付けるべき知識は、自他の人権を尊重したり人権問題を解決したりする上で具体的に役立つ知識でもなければならない。例えば、自由、責任、正義、個人の尊厳、権利、義務などの諸概念についての知識、人権の歴史や現状についての知識、国内法や国際法等々に関する知識、自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知識等が含まれるであろう。このように多面的、具体的かつ実践的であるところにその特徴がある。
2.価値的・態度的側面
この側面の資質・能力は、技能的側面の資質・能力と同様に、人権感覚に深く関わるものである。
人権教育が育成を目指す価値や態度には、人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、多様性に対する肯定的評価、責任感、正義や自由の実現のために活動しようとする意欲などが含まれる。人権に関する知識や人権擁護に必要な諸技能を人権実現のための実践行動に結びつけるためには、このような価値や態度の育成が不可欠である。こうした価値や態度が育成されるとき、人権感覚が目覚めさせられ、高められることにつながる。
3.技能的側面
この側面の資質・能力は、価値的・態度的側面の資質・能力と同様に、人権感覚に深く関わるものである。
人権の本質やその重要性を客観的な知識として知るだけでは、必ずしも人権擁護の実践に十分であるとはいえない。人権に関わる事柄を認知的に捉えるだけではなく、その内容を直感的に感受し、共感的に受けとめ、それを内面化することが求められる。そのような受容や内面化のためには、様々な技能の助けが必要である。人権教育が育成を目指す技能には、コミュニケーション技能、合理的・分析的に思考する技能や偏見や差別を見きわめる技能、その他相違を認めて受容できるための諸技能、協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、責任を負う技能などが含まれる。こうした諸技能が人権感覚を鋭敏にする。
引用:文部科学省:人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]-指導の在り方編-, 2008
必然的領域に重点を置いた学級経営を実践していくためには、自他を認めることや言葉の大切に関する授業を同時に実践していくことが大切です。
人権教育は、多文化共生社会の実現を理念とし、国際的な観点から差別や偏見の是正を推進していくための教育活動です。
コロナ禍にある現在、多様性を尊重していく観点から差別や偏見を是正し、自他を尊重していくための資質・能力の育成は益々重要性を増しています。
教室の必然的領域を大切にするためには、学級経営と授業を同時に実践していくことが重要です。両者を同時に進めることで相乗効果が生まれます。
まとめ
「必然的領域」と「計画的領域」と「偶発的領域」
② みんなの居心地がよい学級経営をするために「必然的領域」が最重要である
必然的領域は、子どもたちの人権を保障するための指導であり、毅然とした指導を全ての教職員で実践することが必要です。また、教師の人権感覚が問われる領域であると共に、教師が子どもや自分を守るためにも大切な領域です。
③ 人権教育(必然的領域)の学級経営の理論はPDCAサイクルである
①児童生徒の実態の把握→②学級集団作りの目標の設定→③地域や保護者との連携→④生徒指導や言語などを含めた学級の風土の醸成→⑤学級経営の点検・評価による改善→① 児童生徒の実態の把握 というようにPDCAサイクルを理論として説明しています。
④ 人権教育を通じて育てたい資質・能力を授業実践で育成する
「人権教育を通じて育てたい資質・能力」は主に3つの側面(「知識的側面」、「価値的・態度的側面」、「技能的側面」)があります。それらをバランスよく育成していくことが、自他の人権を尊重していく行動へとつながります。
本ページでは学級経営の理論を主に説明しましたが、本サイトでは具体的な学級経営の方法や授業実践についても紹介していますので参照していただけると幸いです。なお、理論と実践を往還させるための研究を広げたいと思っているので、本サイトが気に入ったら他の方にも紹介していただけると嬉しいです。
関連