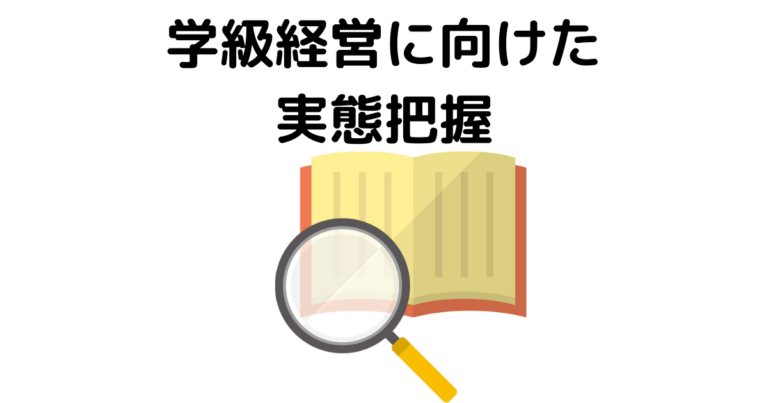学級経営はスタートが大切です。
そのため、教師は学級経営の準備を子どもたちと出会う前から準備をする必要があります。
学級担任をもつことが決まったら、これから担当する子どもたちの個性を把握しましょう。
この記事では、学級経営の一番はじめに行う子どもたちの実態把握の方法について説明します。
新1年生を担任する場合
新1年生の担任になる場合は、子どもたちの実態に関する情報が限られています。様々な教職員と連携して子どもたちの実態を把握しましょう。
① 校内の先生方からの聞き取り
新一年生の子どもに関して詳しい先生方は、管理職の先生(校長先生や副校長先生)、保健室の先生(養護教諭)、栄養士(栄養教諭)、現在の1年生の担任です。
上記の先生方は、就学時検診を実施したり、保育園や幼稚園、認定こども園の先生方から子どもたちの様子についての引継ぎを受けたりしていると思われます。また、入学前に保護者と面談をしている場合もあります。
そのため、上記の先生方と打ち合わせをする機会をもち、新一年生の児童の実態についての引継ぎを受けましょう。
例えば、食物アレルギー疾患であることや持病があるなど、授業や給食時に配慮が必要な児童の担任になる場合があります。
これらの実態を適切に把握しておくことで、座席の準備や給食の運営方法を準備することができます。
新1年生の担任が子どもたちと一番初めに出会うのは入学式の時です。
教師は入学式の前から児童の実態を適切に把握することによって、子どもたちの人権を尊重していくための学級経営の準備を進めることが大切です。
② 保育所・幼稚園・認定こども園から送付された指導要録の確認
幼児教育と学校教育の連携をスムーズかつ確実に実施していくために、公簿による引継ぎが行われます。
小学校にはこれから入学してくる子どもたちの様子について記述された要録が送付されます。
この指導要録には、保育者たちが一人ひとりの子どもの様子について記録されています。
新一年生の担任になった要録を活用して、これから出会う子どもたちの個性について把握しましょう。
2年生~6年生の担任をする場合
2年生~6年生の担任をする場合は、子どもたちの実態に関する情報が蓄積されています。前担任の引継ぎを中心にしながら、実態の把握を行いましょう。
① 前担任の先生や専科の先生方からの聞き取り
昨年度まで在籍していた場合は、多くの先生方との関わりがあるので、子どもたちの実態を把握する情報は多いと思います。
とりわけ、前担任は1年間、授業や生活指導を実践してきたので、児童の実態についてもっとも詳しいです。
新学期が始まる前に、引継ぎをしっかり行いましょう。
一方で、健康状態など課題がある児童については、前担任の先生だけではなく、これまでに担任をしたことがある先生方や養護教諭や栄養士からも個別に聞き取ることも大切です。
担任として子どもたちと一番初めに出会うのは始業式です。
始業式の前に児童の実態を適切に把握し、子どもたちの人権を尊重していくための学級経営の準備を進めましょう。
② 小学校指導要録の確認
小学校では年度末までに指導要録に記録を残すことが義務づけられています(学校教育法施行規則 第24条)。
内容については以下のようになっています。
○在学する児童生徒の学習の記録として作成するもの。
○「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」からなる。
○「指導に関する記録」としては、
行動の記録や、教科・科目の学習の記録、→観点別評価(小中のみ)、取得単位数(高校のみ)、
評定(小3以上及び中高)
評定(小3以上及び中高)
総合的な学習の時間、特別活動の記録、総合所見及び指導上参考となる諸事項 などを記載。
なお、指導要録の保存年限は、指導に関する事項は5年。学籍に関する事項は20年となっています。
詳細については、文部科学省のHP「指導要録について」をご覧ください。
これらは、子どもたちの実態把握に欠かせないものですから、一人ひとりがどのような学びを積み重ねてきたのかを知るためにとても役立ちます。
担任になったら、子どもたちの指導要録を確認するようにしましょう。

子どもたちは一人ひとり違います。だからこそ、子どもたちとの出会いの当日に向けて実態把握は学級経営で大切な要素です。一人ひとりを尊重していくためには、子どもたちの個性をはじめに把握するようにしましょう。