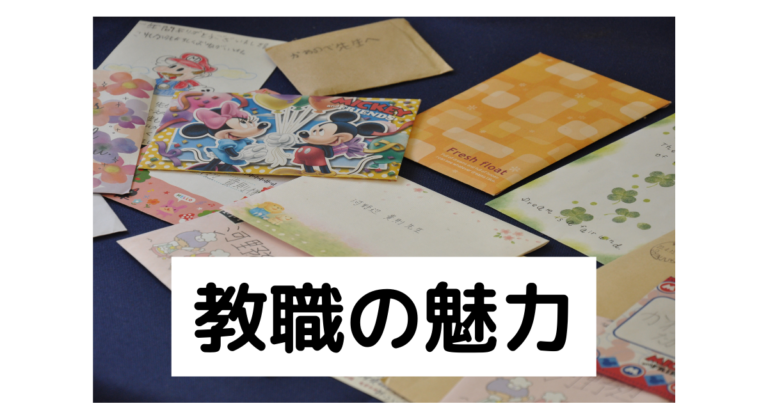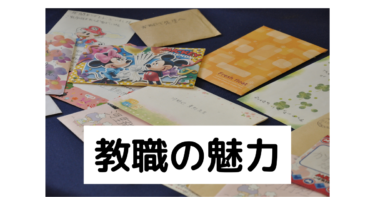教師の仕事は忙しいと言われています。また、子どもたちの命を預かるうえでも責任ある仕事です。
でも、教師の仕事は、人を育てることの喜びや自分自身が成長できる魅力もあります。
この記事では、教職の魅力を解説していきます。
教え子から突然の手紙がポストに届く時

学校の先生になってから、教え子や保護者の方々にいただいたお手紙は、今でもすべて大切に保管しています。
年賀状や暑中見舞いはもちろんですし、、離任式でいただいた手紙や年度末に個人的にお手紙を渡してもらったこともあります。
なお、教え子や保護者だけからだけではなく、時にはスクールカウンセラーや図書ボランティアの保護者の方などからもお手紙をいただきました。
さらに、卒業生として送り出した教え子から、3年後に自宅のポストに送られてきたこともあります。
そして、2020年の4月のコロナ禍の折に初めての緊急事態宣言が発令されたときにも自宅のポストが届きました。

若手だとしても即戦力として活躍することができる

学校の先生の勤労の喜びを感じられる理由の一つとして、若手だとしても即戦力として活躍できる機会に恵まれることが挙げられます。
子どもたちにとって、若手教員であろうが、中堅教員、ベテラン教員も関係ありません。
自分の担任の先生は、唯一無二の存在です。

わたしは、初任者の年度末に保護者の方からお手紙をいただくことがありました。
そこに綴られていたのは、「子どもを大切にしてくれたことに対する気持ち」や「クラスのお友達との輪が広がったことへの感謝の気持ち」等が綴られていました。
「学校の先生」の力量は、教職経験年数だけで決まりません。
[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]が当たり前になる学級経営や生徒指導、授業実践等、人権教育を基盤とした教育活動を実践することができるのかが大きなポイントです。
もちろん、若手だとしても学校の先生としての責任も当然負うことになります。
人権感覚をしっかり磨き、子どもたちの人権を尊重していく役割を果たすことは必須です。
教えるために自分自身も成長し続けることができる
人に何かを教えるためには、教材研究する必要があります。
わたしは、教材研究のためのフィールドワークに様々なところにでかけました。
近い所だと近所のコンビニを取材しました。
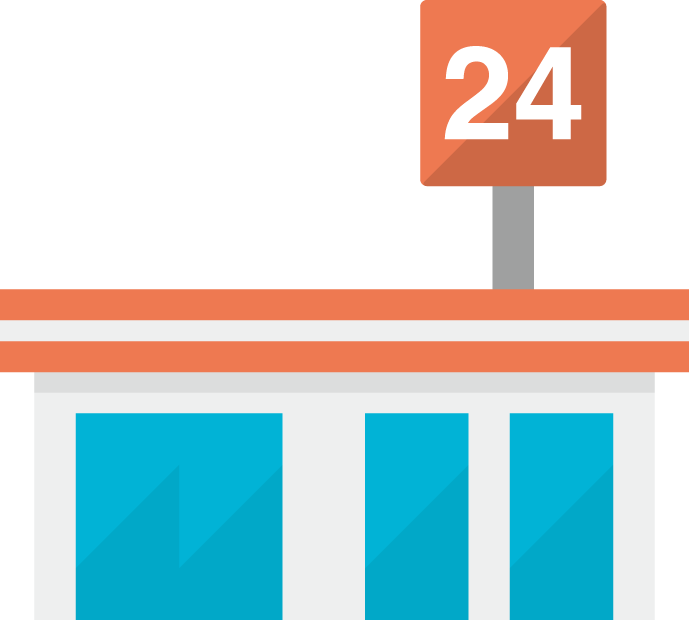
東日本大震災後の被災地にも訪問しました。

一番遠い所は、ポーランドのアウシュビッツ強制収容所でフィールドワークを行いました。

テレビ番組だって録画しておけば、立派な動画教材になります。

教材研究を通して、新しい学びがたくさんありました。
「人は教えることによって、もっともよく学ぶ」
哲学者のセネカの名言で締め括りたいと思います。