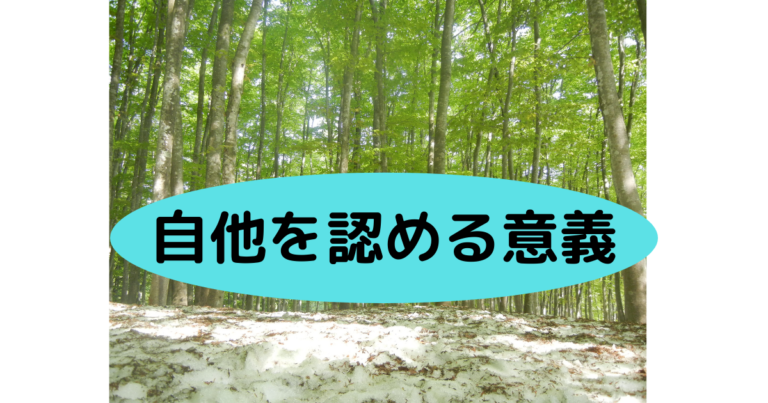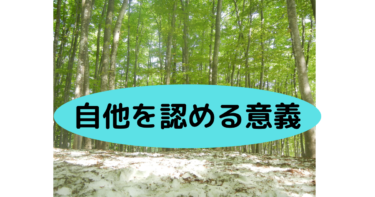この記事では、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」を解説します。
文部科学省の見解について
「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」とは、文部科学省が人権教育の基本理念を分かりやすく伝えるための説明です。
以下に、文部科学省のHP「人権教育の基本的な指導の在り方[第三次とりまとめ]」からの引用を記します。
この[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]については、そのことを単に理解するに止まることなく、それが態度や行動に現れるようになることが求められることは言うまでもない。すなわち、一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることが、人権教育の目標である。
そして、人権教育を通じて育てたい資質・能力は、大きく3つの側面があることを説明しています。
これらを複合的に育むことによって、「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動」につながることを構造として掲げています。
研究者の論考との関連
自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるためには、「共同体道徳」(松下,2011)が重要な要素の一つだといえます。
「共同体道徳」とは、特定の時代や社会の文化的条件を考慮しながら、一定の共同体の内部で成立する規範のことを指します。
そして、共同体道徳は、共通の問題に対して対応している人々のあいだで、その行為がもたらすものの価値づけに対して、互いに呼びかけ応えることによって自主的に生まれるものです。
なお、共同体道徳は、集団の厳しい掟だと誤解される面があります。
共同体道徳は本来、異質な文化や排他的な価値観によってそれ自身が変化していく可能性に開かれています。
すなわち、問い続けることによって、破壊と再生を繰り返し、新しい規範を生み出すことにつながります。

参考文献:松下良平『道徳教育はホントに道徳的か?』,日本図書センター, 2011年。
自分の大切さと共に他の人の大切さを認める子どもたちを育むために
人権教育は、一つの教科や領域だけでなく、学校の教育活動全体で取り組むことが特徴です。
そのため、教科横断的に取り組み、人権教育を通じて育てたい資質・能力を育成していく必要があります。
だから、学級経営や生徒指導、授業づくり等、様々な場面で指導をすることが可能となります。
具体的な人権に関する授業づくりや、学級経営の方法については、
「自他を認めるための授業実践の具体例を紹介します」や、「小学1年生の学級経営のコツを解説します」を
参考にしてください。
一人ひとりの人格を尊重していく、社会の基盤として人権があります。
そして、人権が尊重されている教室は、子どもたちの学びを保障し、一人ひとりの成長に欠かすことができない要素です。
「自分の大切さととともに他の人の大切さを認める」こととは、教師や子どもたちが対話し、呼びかけー応えていくことによって、少しずつ培われていきます。