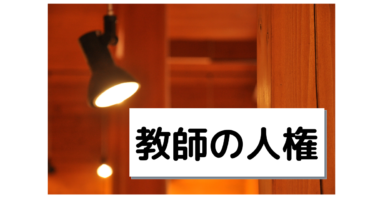この記事では、教師が人権を学ぶことによるメリットについて説明します。
学校教育を推進していくためには、学校の先生も人権を尊重されるべき存在であることを意識することが大切です。
学校の先生には、未来の子どもたちを育成していくという重責を担っています。
また、教育公務員としての職責を果たすことが社会から期待されています。
つまり、人権教育は子どもたちを大切にするだけでなく、教師自身が自分を大切にしていくことにも力を与えてくれます。
判決書から学ぶ教師の人権
中学校教諭の過労死(1998年12月12日自殺)(2012年2月23日大阪高裁判決)
○社会通念上程度に過重な心理的負荷という判断
9月頃には教諭の帰宅時間が1学期に比べて遅くなり、疲れた様子で壁を向いて正座し下を見ながら座っていることもあった。
10月頃には、それまで行っていた風呂の準備をしなくなり、夕食時も家族の会話に耳を傾けず、下を向いて無言で食事をするようになった。
10月頃から、学校でも、空き時間にうつ伏せになっていることが多くなり、同僚教員に「あまり寝られない」ということがあった。
個々の問題ごとにみれば、教師として学級担任になれば多くの教師が経験するものであったとしても、
A教諭が98年4月~10月にかけて負担した心理的負荷の強度は、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重な心理的負荷というに十分である。
参考文献:梅野正信『教育管理職のための法常識講座』上越教育大学出版部,2015.
子どもには人権があります。そして、教師にも人権があります。
教師だからといって、過重な心理的負荷を受け続けたりすることが認められるわけではありません。
教師の人権を守る必要性は、判決書によっても明示されています。
教師の人権感覚については、「1%の「もしかしたら」を想像する人権感覚と声かけが、居心地がよい学級経営には欠かせません」をご覧ください。
学級の秩序を守るための法令による規定
公立小中学校における出席停止制度は、学校教育法第35条に規定されています。
「性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命じることができる」とされています。
なお、この制度は、出席停止を命じる児童生徒本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。
そのため、組織的な対応としての在り方も同時に求められます。
先ずは、同僚や管理職に相談しましょう。
一方で、このような状況にならないためには、人権教育を推進し、学級崩壊を予防をすることがもっとも重要です。
学級崩壊に関する記事は「学級崩壊を予防するためのポイントを解説します」をご覧ください。
教師は自分の人権を守ることを意識することも大切です。
教師も自分の人権を大切にする
子どもたち一人ひとりを大切にすることは教師の責務です。
一方で、教師だって人間ですから、悩みを抱えていたり、体調が優れないときがあります。
自分の心のケアや体調のケアを教師は行うことが大切です。
世界人権宣言第24条には、
「すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する」
と明示されています。
そして、日本では「労働基準法」が施行されています。
教師が心のバランスや健康状態をセルフコントロールし、人生を充実させることは、結果的に子どもたちにメリットをもたらします。
教師が心も健康であることが大切なのです。
なお、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の第31条に「子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります」と明示されています。
子どもたちの大切な休み時間を安易に奪ってしまうことは、控えるべきです。
教師は、自分の人権と子どもたちの人権を双方に尊重していくことが大切です。
なお、学級経営をサポートするために給食指導や席替えの指導、授業実践に関する記事等を「学級経営で大切なこと<河野辺研究室>」に掲載しています。また、健康を留意していく観点から「週末に心を整えるための方法を紹介します」も掲載しているので、お時間があったらご覧ください。