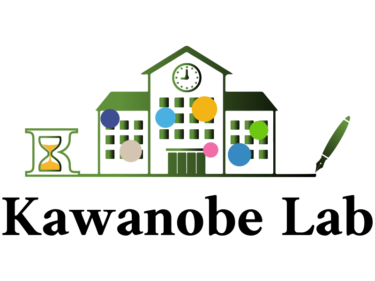学校教育の実践の場には、様々な教育課題や悩みを抱えている児童生徒や、児童生徒を指導していく上で、様々な悩みを抱えている先生方がいらっしゃいます。
私自身も東京都の公立小学校(八王子市、新宿区、調布市)に14年間勤務していましたので、学校教育の実践の場で児童生徒を指導していく際に困難な課題に直面し、様々なことを経験して参りました。
一方で、教師として働くことの面白さも経験して参りました。
その面白さの軸は「学級経営」にあったと思います。
学級経営は、授業や生活指導、保護者対応など、様々な構成要素があります。
とりわけ、わたしが大切にしてきたことは、子どもたちの居心地です。
この居心地は、白松(2017)の「学校・学級づくりの三領域」でいうところの「必然的領域」にあたります。
例えば、白松(2017)は、必然的領域の指導を「児童生徒の一人ひとりの多様性を尊重」、「どの教師も、どの児童生徒へも同じように指導」、「自己と他者の人権や文化的背景を大事にする」と明示しております。
わたしは、学級の居心地をよくしていくためには、[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]への指導が重要だと考えています。
これは文部科学省が、人権教育の目標を分かりやすく表現している言葉のことです。
すなわち、居心地がよい学級経営をしていくためには、人権尊重の視点が重要であり、その実現に向けて実践を重ねてきました。
私の研究室では、人権教育の観点から学校教育を研究し、社会や学校教育の実践の場に還元することを目指して研究活動を進めております。
人権教育に関する研究成果を学校教育の実践の場に「居心地がよい教室」という文化を定着させるための一助になることを願って、
授業実践や学級経営、生徒指導等について人権教育の観点から、ブログを綴りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

参考文献:白松賢『学級経営の教科書』,東洋館出版,2017.